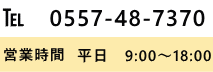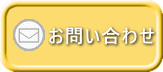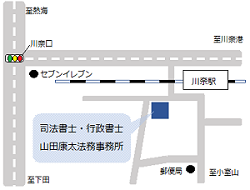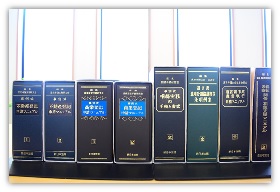伊東市の司法書士・行政書士山田康太法務事務所 | 伊東市・熱海市・東伊豆町の相続・遺言・登記の相談
受付時間:月〜金曜日 9:00〜18:00
不動産登記不動産登記
不動産登記とは
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することのより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。

所有権移転
売買
Aさんの不動産をBさんが買うと、その所有者がAさんからBさんへと変わります。これを法律的には「AからBに所有権が移転した」と言います。不動産売買の場合は、通常このことを登記簿に記録します。不動産に関する権利を第三者に対して主張するためには、登記をしなければならないからです。
 必要な書類(売主)
必要な書類(売主)
- 運転免許などの本人確認書類
- 登記権利証(登記識別情報)
- 印鑑証明書
- 実印を押した委任状(司法書士作成)
- 押印した登記原因証明情報(司法書士作成)
- ※不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要となりますので、不動産の固定資産評価証明書も必要です。
- ※売買物件に抵当権がついている場合は、それを抹消してから所有権移転登記をすることになります。そのため、金融機関からもらう書類(解除証書、登記済証など)と売主からの委任状も必要になります。
- ※物件の登記簿に載っている住所・氏名と、売主の現住所・氏名が異なる場合は、登記名義人住所(または氏名)変更の登記を先に行います。そのため、2つの住所(氏名)のつながりを証明する住民票や戸籍の附票などが必要になります。
 必要な書類(買主)
必要な書類(買主)
- 住民票
- 押印した委任状(司法書士作成)
- 押印した登記原因証明情報(司法書士作成)
贈与
代金の支払いを伴う売買とは異なり、無償で相手方に財産を与え、相手方がそれを受け入れることで成立する契約を贈与といいます。贈与によっても不動産の所有権が移転しますので、売買と同様に所有権移転の登記を申請します。
贈与による登記には、土地売買や住宅関係登記のような登録免許税の軽減措置がなく、印紙代がやや高額になります。
また、贈与税がかかることにも注意が必要です。
 必要な書類(贈与する方)
必要な書類(贈与する方)
- 印鑑証明書
- 権利証
 必要な書類(もらう方)
必要な書類(もらう方)
- 住民票
※ 司法書士が「贈与契約書」を作成します。
建物の新築
所有権保存
新築した建物は登記簿に記載されていません。そこでまず、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記録する「建物表題登記」をすることになります(土地家屋調査士)。その後に、司法書士が、所有権などの法的権利を第三者に対抗するための「所有権保存登記」を申請することになります。
 必要な書類
必要な書類
- 所有者の住民票
- 委任状(司法書士作成)
- 住宅用家屋証明書 等
抵当権設定
建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記が完了すると、金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。
登記名義人住所(氏名)変更
不動産の登記名義人が引越しや結婚などで住所・氏名が変わったとき、住民票の記載を変えたからといって登記簿まで自動的に書き換わるわけではありません。登記名義人住所(氏名)変更登記を申請します。
住宅ローンの完済
抵当権抹消
住宅ローンの借入をする際に、ほとんどの場合はその土地や建物に抵当権を設定する登記をします。しかし支払いが完了した後、その抵当権の登記は自動的に消えるのではなく、登記簿上の抵当権は当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、いろいろな不都合が生じます。
住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。
 必要な書類
必要な書類
- 金融機関の抵当権設定権利証又は登記識別情報
- 解除証書
- 委任状(金融機関及び住宅の所有者)
このようなときは、ご相談ください。
- 土地や建物を買ったとき、もらったとき、相続したとき。
- 土地が祖父の名義のままになっている。
- 家の名義を子供にしたい・妻と半分にしておきたい。
- 不動産の個人間売買をしたい。
- 建物を新築したので登記をしたい。
- 住宅ローンで土地や建物を担保にお金を借りたとき。
- 住宅ローンを完済し土地や建物についた担保を抹消するとき。
- 離婚によって不動産を財産分与するとき。
- 昔からの共有名義を解消したいとき。